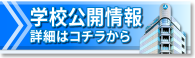ノベルス・シナリオ業界には、あらゆるジャンルの文章や作品が存在します。
その中でも、特に10代〜20代の若い世代に圧倒的な人気を誇るのが「ライトノベル」です。
今回はノベルス・シナリオ業界において欠かせない、ライトノベルに注目して見ていきましょう。
ライトノベルブームとは
ライトノベルはコミックイラストが多く使われ、文体も読みやすいものが多いことから、本に馴染みのある層よりは、アニメやマンガが好きな層からの人気が高いです。
今や知名度のあるライトノベルですが、その地位を確立したのは意外と最近のこと。
特にメディアミックスと呼ばれる、一作品でアニメ、小説、映画等幅広く展開する手法がよく使われる現代では、アニメやマンガをきっかけにライトノベル作品が注目される機会が増えています。
日本には三回のライトノベルブームがあった
実は、日本のライトノベルブームは三回あります。
時代ごとに、ライトノベルブームを説明していきましょう。
最初のブームは1980年代後半から1990年です。
当時も中高生を中心にライトノベルが流行し、ファンタジーブームになりました。
続いてのブームは2004年頃です。
爆発的な人気を誇る作品が多く、アニメ化や映画化もされて話題になりました。
逆に、アニメや映画を観て原作のライトノベルを読んだというファンも多く、この頃からメディアミックスの流れができていたように感じます。
直近のブームは、2010年ごろです。
インターネット上にライトノベルが多く投稿されるようになり、投稿専門サイトも増えました。
そのまま書籍化された作品も数多くあります。
ライトノベルが支えるノベルス・シナリオ業界の市場
世界観がアニメやマンガに近いライトノベルは、本や活字に興味がなくても気軽に楽しむことができます。
そのためか、ライトノベルの作品数は2007年からの10年間で約2倍に増え、電子書籍での市場規模も拡大傾向にあります。
このようにライトノベルは、ノベルス・シナリオ業界の市場を支える重要な役割を果たしています。
ライトノベルブームの中でも読まれる小説を書くには
さて、ここまでライトノベルブームについて解説してきましたが、中にはライトノベル作家をめざしているという方もいるのではないでしょうか。
すでに趣味でライトノベルを書いているという方もいるかもしれません。
また、たとえライトノベルではなくても、小説家をめざすなら読まれる小説の書き方を知っておく必要があります。
皆さんが小説を書く際、何を一番重要視するでしょうか。
ストーリーでしょうか、登場人物でしょうか、あるいは風景や心情の描写でしょうか。
しかしどんなに優れた小説でも、「読みたい」という感情を読者に持ってもらわないと、何の意味もありません。
今回は読者を小説に引き込む導入となる部分、「タイトル」についてお話します。
読まれるタイトルのつけ方とは
「タイトル」は言うなれば小説の「顔」となる部分です。
読者はタイトルから得られるインスピレーションと冒頭部分をチェックして、自分が求める作風かを判断します。
ですからタイトルをつける際は、それが「作風にふさわしい表現」であり、「作品のにおいを感じさせるもの」が理想的で、読者に期待を持たせるタイトルにするのが良いでしょう。
タイトルのつけ方のパターン
タイトルのパターンは大きく分けて以下の五つがあり
・ライトノベルでよく見かける「台詞をタイトルに使う」手法。
・作中の舞台や世界観を表現した「物語の内容をそのまま使う」手法。
・キャラクターの魅力をより前面に押し出すことができる「主人公の名前を使う」手法。
・作中のキーワード等を短くし、意味深な雰囲気を持たせる「イニシャルを使う」手法。
・“魔法”や“悪”といった言葉を用いた「物語のテーマを感じさせる」手法。
他にも多くのパターンが存在しますが、ここで重要なのが、タイトルは「自由な発想でつけて良い」ということです。
他の作品を参考にしすぎて、オリジナリティを損ねることや、作品との差異が生まれてしまうのは好ましくありません。
自分の作品がどんな物語であるかは、筆者であるあなた自身が一番よく理解していると思います。
それをちゃんと理解していれば、自然とタイトル候補も思い浮かぶことでしょう。
タイトルは読者を導くことができる唯一の存在です。
読者の購買意欲を揺さぶるのも、物語を読みたい気持ちにさせるのもタイトルです。
まとめ
過去に三回ブームが起こったライトノベルは、読書好きだけでなくあらゆる層からの参入が期待できます。
そのためライトノベルは今後も、ノベルス・シナリオ業界を牽引していくことでしょう。
ライトノベルブームにともない、今後ライトノベル作家も増えてくるかもしれませんね。
これらの点を踏まえ、皆さんがより充実した創作ができることを、デジタルアーツ東京は期待しています。